ナスは水分が多く、身体にこもった熱を冷ましてくれる効果があり、夏野菜の定番ですね。
今回は、堆肥をまき肥料食いの野菜としても有名なナスを苗から植え付けた様子をお伝えします。
このブログは、家庭菜園でナスの苗を植えた時に行った対策と植え付けた品種の特徴について書いています。
植え付けた品種の特徴
オーナーさんに用意して頂いていたナスのラインナップから、中長ナス「千両二号」、丸ナス「泉州絹皮水なす」、米ナス「くろわし」、楕円白ナス「とろーり旨なす」を選びました。
中長ナス「千両2号」

長卵形ナスの千両2号はアクが少なくて、まろやかな口あたり。
どんなお料理にも使える万能品種。
特徴:皮が厚く、実が引き締まっている。
長卵形ナスの中でも「千両」「千両2号」はたくさん取れて作りやすいので日本全国に広がっているそうです。
丸ナス「泉州絹皮水なす」

大阪の泉州地域の伝統野菜。
果皮が薄くてアクも少ないため生食にも向いている。
泉州地域では、まるごと1個をそのままつけた「水ナス漬け」が有名。
水ナス栽培には難しい印象がありましたが、家庭菜園でも挑戦できるようなので初心者でも成功できるか期待大です。
米ナス「くろわし」

収穫までが早く収穫量が多い。
多少取り遅れても肉質の低下が少ない。
育てやすい品種なので、家庭菜園にも最適。
収穫期を過ぎても色あせもしないそうなので、週末農園には向いていますね。
楕円白ナス「とろーり旨なす」

果皮は通常の白ナスより柔らかく、加熱するとねっとりとした触感になる。
栽培方法は、普通のナスと同様。
白ナスの果皮は硬い印象がありますが、この品種は他の白ナスより柔らかいらしいのでお料理しやすいですね。
植え方や肥料について
ナスは肥料をたくさん必要とする野菜として知られており、「肥料食い」とも呼ばれています。
肥料切れにならないように、追肥をしていくそうです。
オーナーさんの説明では「追肥でもいいですが、心配なら堆肥を入れてみましょう。パラパラとまいて軽く耕しましょう」とのことでした。
まーちゃんガーデンの畝の約半分でナス4本を栽培することにしました。
株間は60cm程度で千鳥植えを教わりました。

バケツに5分1程度の堆肥をまきました。
苗は接ぎ木苗でした。
接ぎ木苗は病害虫や連作障害に強く、根がしっかり張って株の勢いが長持ちするそうです。
だから、接ぎ木苗は多くの収穫が見込めるんですね。
接ぎ木のクリップは1週間程度で取り除くそうです。
忘れないようにしたいと思います。
【ナス苗から育てる】のまとめ
畝にポットの大きさに合わせて穴を掘って水を撒き、ポットをさかさまにして苗を取り出して穴に植え、再度水を十分に与え、苗の周りの土を落ち着かせました。
次は、支柱立てかな?と思いましたが
オーナーさん曰く「5月までは、不織布のネットを掛けておきましょう。」
「まずは、苗が環境が変わっても元気に生育できるように保護するのがいいと思っています。支柱は5月以降ですね。」とのことでした。
やり方は一様ではなく土地や気候などの条件や育てる人の創意工夫があるんですね。

今日は春らしい陽光に照らされ穏やかな日でした。
春から夏にかけては家庭菜園本番の季節ですね。
追肥と水やりで忙しくなりそうなまーちゃんガーデンです。
参照元:旬の食材百科事典
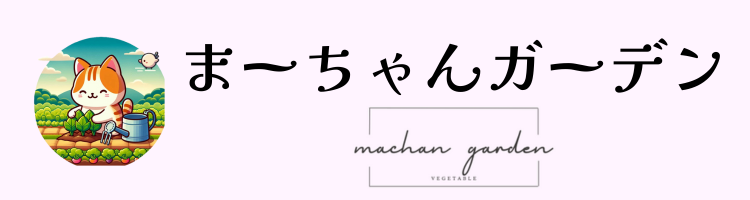


















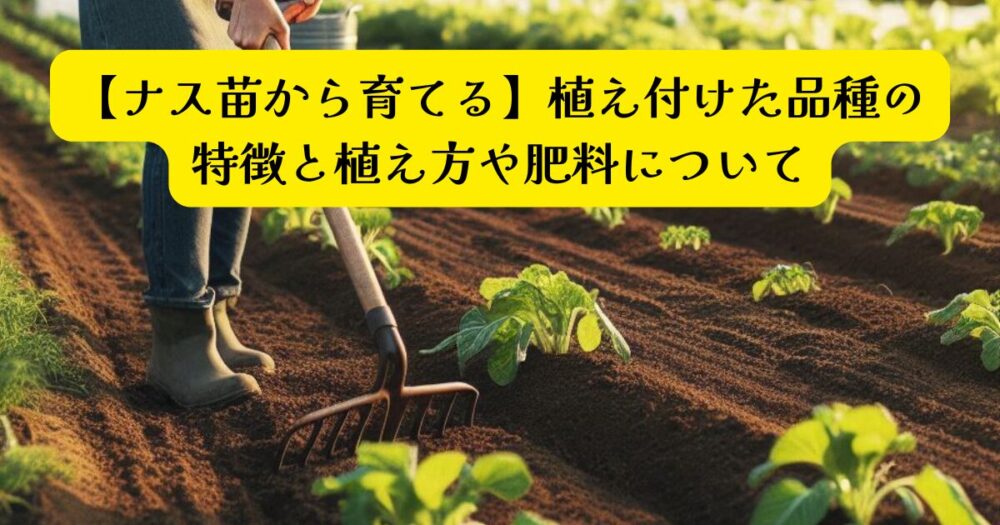
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed8331.c003d4fa.46ed8332.43afc40b/?me_id=1287623&item_id=10004906&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fteshimanonaeya%2Fcabinet%2Fgift%2F1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



