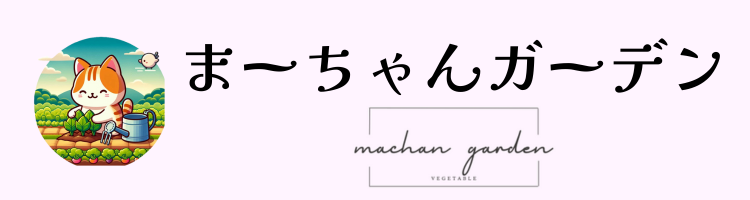最近はサラダ水菜(早生)が人気ですが、水菜といえば本来は冬の野菜。
漬物や鍋料理に使われる、シャキッとした歯ごたえと香りが魅力です。
私の菜園でも、育苗を始めたところです。
目指すのは、昔ながらの「晩生千筋京水菜(ばんせいせんすじきょうみずな)」を大株に育てて、冬の食卓でたっぷり楽しむこと。
今回は、初心者でも安心して育てられるように、間引きと株間のポイントを中心に「晩生千筋京水菜」の育て方をご紹介します。
晩生千筋京水菜(ばんせいせんすじきょうみずな)とは?
京都の伝統野菜として知られる「千筋京水菜」は、深い切れ込みのある緑の葉と、繊細で細く白い葉軸のコントラストが美しい品種です。
晩生タイプはゆっくり育ち、寒さに当たることで甘みと風味が増します。
サラダ向けの早生品種とは違い、漬物や鍋にぴったりの大株に育てるのが醍醐味です。
水菜(ミズナ)の育て方
株間と間引きのタイミング
種まきは9月中旬〜下旬が適期です。
【条まきの場合】
発芽後、本葉が2〜3枚出た頃に最初の間引きを行い、株間2〜3cm程度に整えます。
水菜は害虫がつきやすいため、種まきと同時に防虫ネットをかけるのがおすすめです。
次に、本葉が4〜5枚になった頃に2回目の間引き行い株間を10cm程度に広げます。
これにより根張りがよくなり、しっかりした株に育ちます。
大株に育てたい場合は、本葉6〜8枚の頃に最終間引きを行い、株間30〜40cmを確保するのが理想です。
セルトレイ育苗の場合
1セルに2〜3粒の種をまき、本葉2枚の頃に間引を行い、本葉4〜5枚になれば畑に植え付けます。(発芽適温20~25℃)

株間を広く取る理由
水菜は根が浅く広がる性質があるため、株間が狭いと養分や水分の取り合いになり、ひょろひょろした株になってしまいます。
特に晩生品種は時間をかけて育つので、株間を広くとることで、茎が太く、葉がしっかりした大株に育ちます。
また、風通しが良くなることで病害虫の予防にもつながり、冬場の寒さにも強くなります。
育て方のコツ
●土作り
植え付けの2週間ほど前に堆肥や石灰、肥料を混ぜて耕しておきましょう。
●水やり
水菜は水はけの良い土壌を好みますが、生育初期には十分な水分が必要です。
●追肥
株の生育を見ながら2~3回行います。
(肥沃な土壌を最初に作っておけば追肥は不要と書かれているものもありました。)
●収穫
草丈が30〜40cm、重さ1kg前後になったら、根元から収穫します。
まとめ|冬の水菜を楽しむために
間引きと株間の調整が大株育成のカギです。
大株に育てるなら、株間が広く取りやすい点まきが向いているようです。
私の菜園では、15㎝間隔で点まきし、間引き(収穫)をしながら株間を広げていき、最終的に大株に育てていきたいと思っています。
この栽培方法だと、小株のやわらかい水菜を楽しみながら、大株に育てることができそうです。
晩生千筋京水菜は、時間をかけて育てることで、冬の食卓にぴったりの味わい深い野菜になります。
「サラダ水菜もいいけれど、やっぱり冬の水菜が好き」
そんな方にこそ、ぜひ育ててほしい伝統野菜です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
私の菜園では、晩生水菜の育苗と並行して、8月にまいたブロッコリーや白菜も順調に育っています👉
育苗についてはこちらも参考にしてください。👉
参考元:
・水菜(ミズナ)の栽培方法・育て方 | タキイネット通販
・ミズナ(水菜)の育て方と栽培のコツ | やまむファーム
・ミズナ(キョウナ) 小株から大株まで楽しむ|JA神奈川つくい